STORY
結婚・出産を機に仕事を辞め、育児と家事に追われるジヨン。常に誰かの母であり妻である彼女は、時に閉じ込められているような感覚に陥ることがあった。そんな彼女を夫のデヒョンは心配するが、本人は「ちょっと疲れているだけ」と深刻には受け止めない。しかしデヒョンの悩みは深刻だった。妻は、最近まるで他人が乗り移ったような言動をとるのだ。ある日は夫の実家で自身の母親になり文句を言う。「正月くらいジヨンを私の元に帰してくださいよ」。ある日はすでに亡くなっている夫と共通の友人になり、夫にアドバイスをする。「体が楽になっても気持ちが焦る時期よ。お疲れ様って言ってあげて」。ある日は祖母になり母親に語りかける。「ジヨンは大丈夫。お前が強い娘に育てただろう」――その時の記憶はすっぽりと抜け落ちている妻に、デヒョンは傷つけるのが怖くて真実を告げられず、ひとり精神科医に相談に行くが・・・。
公式サイトより
「女性の生きづらさのカタログ」のような映画です。
韓国は、日本と同じように儒教の影響が強く、男尊女卑、年上を敬い立てる文化。
主人公の名前の「キム・ジヨン」ですが、「キム」は韓国で一番多い姓、「ジヨン」は1982年生まれの女の子に一番多い名前なんだそうです。
ごくごく平均的な女の子であるジヨン、そして、ジヨンのまわりにいる母親、姉妹、職場の同僚などが、社会の中でごくごく当たり前に受けてきた扱いが描かれます。
1967年に日本で生まれた私にとっても、映画の中のエピソードひとつひとつに思い当たることがありました。
女の人生ゲーム
キム・ジヨンの母親や姑の世代では、男の兄弟の進学を助けるために、女の姉妹は自分が勉強するのを諦めて、働いて稼ぐのが当然でした。
結婚した後は家事をすべて担って夫を立てます。
自分が産んだ子どもに対しても、女の子には家事をさせて、男の子は王子様のような特別扱い。
ジヨンの世代になると、自分も教育を受けてから働くことが可能になります。
しかし、結婚して子どもができると、女性のみが「仕事か家庭か」の選択を迫られます。
・パターン1 家庭を選択
仕事と育児の両立は難しいと判断して仕事を辞めると、お気楽な身分だと思われ、「主婦虫」と呼ばれる。
・パターン2 仕事を選択
仕事を「一人前」にしようとすると、実母に家事育児を手助けしてもらうことになる。
そこまでしたにもかかわらず、男性の同僚に「自分で子育てしていないから、子どもに悪影響があるよ」と言われる。
・パターン3 仕事と育児の両立
仕事と育児を親に頼らず両立しようとすると、預け先がなかったりして中途半端な存在と見られ、迷惑がられる。
「じゃーどーすればいいのよっ」て感じですよね。
相容れない男性と女性
女性がそれだけの犠牲を払って教育を受けさせ、立ててあげて、仕事をサポートしてあげている男性がみな頼りないのがまたイタイところ。
家の中では役に立たないのに、家族に何不自由ない生活をさせるほど稼いでくるわけでもありません。
なにせ、職場で犯罪レベルのエロコンテンツを見て盛り上がっているのがせいぜいですからね。
にもかかわらず、子育てをしている女性を見ては「あいつらは楽をしてる」と、まるで自分のほうが損をしているような言い方。
ジヨンがバスの中で痴漢に遭うと、父親は娘を守るどころか「女のほうに隙があるからだ」と説教するのです。
ジヨンの夫のデヒョンはとてもいい人です。かな〜り「当たり」の男と言っていい。
それでも、育児休暇を取る理由として「読書や勉強もしたいし」なんて言っちゃうんですよね。
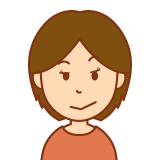
夫デヒョン役のコン・ユがイノッチに似てるから、「あさイチ」での有働アナとイノッチのからみを思い出したよ
女の敵は女?
では、同じ女であれば仲間なのかというと、そういうわけではないところがまた問題の根が深いところです。
姑は、男性を立てて生きてきた自分のように嫁が生きることは当たり前という意識を持っています。
そのため、家族で帰省してきた嫁をコキ使い、夫である息子が皿を洗おうとすると嫁を責めます。
また、妻を気遣って夫が育児休暇を取ろうとすると、わざわざ電話してきて嫁を非難します。
同じ女性でありながら、ジヨンを一番追い詰める存在となっているのです。
自分の声を取り戻すまで

追い詰められたジヨンに出た症状が「憑依」であるのは象徴的です。
ジヨンの苦しみは、ジヨンの個人的な苦しみではない。
ジヨンの苦しみを代弁する「声」は、憑依した女性たちの苦しみでもあるからです。
そして、それは映画を観ている私たちの「声」でもあります。
「いい妻」「いい母」「いい娘」「いい嫁」であればあるほど、ジヨンは自分の声を上げることができません。
ジヨンを苦しめているのは男尊女卑的な社会ですが、子どものころから「いい子」で生きてきた中で、その社会的な規範を自分の中に取り込んでしまい、自分で自分を縛っているんですよね。
これは女性にとっても男性にとってもいろいろと身につまされるので、観るのがしんどい映画です。
でも、実際の映画から受ける印象は、最初にかまえていたほど重いものではありませんでした。
それは、キム・ジヨン役のチョン・ユミの清潔感に負うところが大きいと思います。
また、「憑依」の状態で放たれるセリフが「よく言った!」というものばかりで、うまくガス抜きをしてくれていること。
「憑依」を挿入することで、いい感じに虚構感があること。
最後に、キム・ジヨンは、「憑依」していない状態で、自分の言葉で、カフェにいる若い男女の会社員に反論します。
会社員たちには通じませんが、それを見ていたママたちに響くものはあったでしょう。
たとえ波風を立てることになったとしても、自分の言葉で自分の気持ちを表明することがすべての始まりになるんですよね。
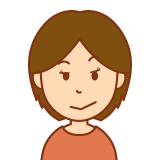
「嫌われる勇気」だね
それが、ジヨンがまた仕事をしているラストシーンへとつながっていきます。
今はまだ見ていてつらくなる「あるある」シーンの連続ですが、いつの日か、いや、できることならば子どもたちの時代には、「あんな時代もあったんだね」と言われるようになっていてほしいものです。
この映画が「時代遅れ」「歴史ムービー」になったときにこそ、この映画の存在意義がまっとうされたということでしょうから。
原作と映画の違いとは
原作小説は、ジヨンを診察する男性の精神科医のカルテという形式になっています。
ジヨンやその母親をはじめとする周囲の女性たちが体験してきたことが比較的淡々と語られていきます。
そして、最終章で、韓国における女性問題を深く理解していると自負している男性医師自身の経験と思いが叙述されるのですが、これが最高の皮肉となって小説は幕を下ろします。
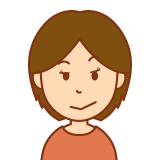
見事な構成!
この小説は、「訳者あとがき」にあるように、「一冊まるごと問題提起の書である。カルテではあるが、処方箋はない。そのことがかえって、読者に強く思考を促す。」という作品です。
映画は、小説にある「カルテ」を再現するだけにとどまらず、その先の「処方箋」を示そうとした作品だと思います。
すぐに社会は変わらないし、1人の声は小さいかもしれない。波紋を起こすこともあるだろう。
それでも前へ進んでいこう、女性だけでなく、夫婦一緒に。
そんな監督からのアンサーを感じました。
おわりに
原作は韓国で130万部のベストセラーとなり、映画も300万人を動員しましたが、日本ではそこまで話題になっていません。
この原作&映画は、たくさんの人に見てもらうことそのものに意味があるタイプの作品です。
そういう意味ではこの作品が話題になったことそのものに韓国の希望があるように感じます。
ひるがえって日本はどうなのでしょうか?
まずは自分が「当たり前」の殻を破るところから始めなきゃ、ですね。

